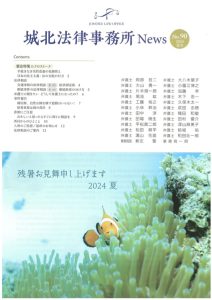城北法律事務所 ニュースNo.91 2025新年号(2025.1.1)
目次
対談 袴田事件再審無罪判決と冤罪事件
【結城】昨年袴田さんがついに再審公判で無罪の判決を得ましたね。
袴田事件は、1966年6月30日午前2時、静岡県清水市の味噌製造会社専務宅が全焼するという火事が発生し、焼け跡からは、専務、その妻、次女、長男の4人が刃物でめった刺しにされた死体が発見された事件です。警察は当初から、味噌工場の従業員であり元プロボクサーでもあった袴田巖さんを犯人と決めつけて捜査し、逮捕しました。
第1審では有罪判決となり、1980年11月19日に最高裁が上告を棄却し、袴田さんの死刑が確定しました。
その後、2回の再審請求を経て2023年に再審開始決定が出て、その後無罪判決が期待されている事件でした。
【和田】袴田さんは、2014年に釈放されるまで長期間にわたって拘束されており人生のほとんどを奪われています。当初は否認を続けていたのですよね。
【結城】そうですね。しかし、警察や検察からの連日連夜の厳しい取調べにより勾留期間の満了する直前に自白しました。その後、公判においては再び否認に転じました。
【和田】結局、公判ではどのような経過をたどったのでしょうか。
【結城】袴田さんは、自白をしたあと、起訴されました。警察の取り調べは起訴後にも続き、自白調書が45通も作られました。袴田氏の自白の内容は、毎回大きく変わり当初は専務の奥さんとの肉体関係があったための犯行などと述べていましたが、最終的には、金がほしかったための強盗目的の犯行であるということになっていました。
【和田】袴田事件のような冤罪事件に限らず警察官や検察官が作成する調書は、被疑者や被告人となった方の言い分をそのまま記載してくれるものではなく、捜査機関側が捜査に都合がよい部分を作文したのではないかと思うものが多いですよね。現に、我々二人が担当し無罪を獲得した公務執行妨害被告事件でも依頼者の方がお話しになっている内容と、公判前に作成された供述調書では内容が食い違うところが多くあり、改めて供述調書の怖さを感じました。
【結城】確かに供述調書は、怖いところがありますね。袴田事件では当初から犯行着衣とされていたパジャマについても、公判の中で静岡県警の行った鑑定があてにならず、実際には血痕が付着していたこと自体が疑わしいことが明らかになってきたところ、事件から1年2か月後も経過した後に新たな犯行着衣とされるものが工場の味噌樽の中から発見され、検察が自白の内容とは全く異なる犯行着衣に主張を変更することになりました。第1審の静岡地裁では、袴田さんに有罪判決を言い渡してしまいました。 それから、再審でも、味噌樽の中からシャツが発見されたことについては問題になっていましたね。味噌樽から発見された5点の衣類は、ズボンには血痕が付着していないにもかかわらずその下に履いているステテコには付着していることになるなど、犯行時に本当に着ていた衣服とは思えないものでした。また、弁護団の実験で1年2か月も味噌につけられていれば衣類はこげ茶色に変色し、血液は黒色に変色することが明らかになりましたが、証拠とされたシャツは白く、血液は鮮血色でした。
【和田】再審公判での静岡地裁の判決でも、捜査機関が証拠を捏造したことを指摘し厳しく非難していましたね。検察官が、明らかに不自然な証拠に基づいて死刑を求刑し続けたことは問題がありますし、今後も検証される必要がありますね。どうして袴田さんは、捜査段階で自分が行っていない犯行を自白してしまったのでしょうか。
【結城】袴田事件では、勾留中トイレに行かせず取調室内におかれた便器に排泄させるなど非人道的な行為があったことも明らかになりました。警察署内の留置施設での自由を奪われ人と話すこともままならない状況で、否認を続けることは非常に困難だったことが容易に想像できます。私たち弁護士が取り組んでいる一般の刑事事件の依頼者の話からも、身体拘束されていること自体が非常にストレスだとわかります。国際的にも日本の刑事制度は、長期間の身体拘束ありきのもので「人質司法」と言われ問題となっています。先ほど紹介した無罪判決を獲得した公務執行妨害被告事件は、依頼者の方が逮捕されてからすぐに警察署での接見を行い、迅速に検察官や裁判所にかけあって検察官からの勾留請求を却下させ、数日で一般社会に戻ることができました。もちろん事情によっては、身体拘束を解くことが難しいこともありますがなるべく早く相談してほしいですね。
【和田】城北法律事務所でも映画「それでもボクはやっていない」のモデルになった痴漢冤罪事件に取り組んだことがありましたね。他にも全国には冤罪事件とされている事件が多くあります。つい最近だと、福井の女子中学生殺害事件というのも、冤罪が疑われて再審が開始になりました。冤罪の原因としては、捜査機関が一定の見込みから取り調べを行い、自白を強要あるいは誘導してしまうことが一つでしょうね。また、捜査機関が税金を使って収集した証拠が被疑者や弁護人には裁判になるまで見られず、自身の有利な証拠などへのアクセスができない点も冤罪の発生を助長していると思います。ところで、袴田事件は、事件の発生が1966年ですね。どうして無罪判決が出るまで時間がかかったのでしょうか。
【結城】時間がかかった原因は、さまざまありますが、再審に関わる刑事訴訟法の規定が不十分であることがあげられます。まず、単なる審理の入り口に過ぎない再審開始決定に非常に高いハードルが課されており、さらに検察官が再審開始決定に自由に抗告できることも原因です。実際、袴田事件の第2次再審請求についても再審開始決定が一度出されていたにもかかわらず検察官が抗告し審理が続いたという経過があります。
【和田】現在、袴田事件を契機に再審法改正の機運が高まっています。これからも刑事事件について尽力するだけではなく、冤罪を防ぐためにいろいろな方面に積極的に取り組んでいきたいですね。