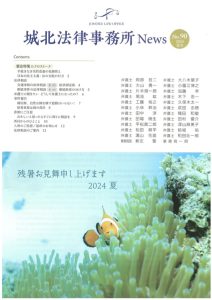城北法律事務所 ニュースNo.91 2025新年号(2025.1.1)
目次
法律相談 模擬法律相談(相続)
弁護士 片木 翔一郎
法律相談ってちょっと敷居が高いとよく言われます。そこで、法律相談がどのような流れで始まるのかの一例をご紹介します。今回は丸雄(まるお)さん(東京都豊島区 70代男性)が遺言作成の相談に来たようですね。
【弁護士】本日はよろしくお願いします。さて、電話でご予約いただいた際には、相続の相談とだけお聞きしておりますが、どのようなご相談でしょうか。
【丸雄】いやね、長男から親父もいい年なんだからそろそろ遺言を作ってくれって言われちゃって。妻の丸子もその方が残される私も安心だからそうしなさいなんて言うもんだから、それで来てみたんです。妻とは少し年が離れているもんだから、私の死んだ後のことが心配みたいで。
【弁護士】そうなんですね。まずは家族関係を簡単にお聞きしていきますね。丸子(まるこ)さんとの間にお子さんは何人いらっしゃいますか。
【丸雄】2人で、両方男です。
【弁護士】念のためお聞きしますが、すでに亡くなったお子さんがいるとか、あるいは丸子さん以外の女性との間にお子さんがいるといったご事情はありませんか。
【丸雄】ないです。
【弁護士】2人のお子さんはご結婚なさっていますか。
【丸雄】両方結婚していて、子供、つまり私から見た孫が1人ずついます。いずれも女の子です。
【弁護士】ここまでにお聞きした内容を家系図にするとこうなりました。そうすると、仮に現時点で丸雄さんが亡くなった場合の相続人は丸子さんと2人の息子さんということになります。もちろんこのなかで丸雄さんより先に亡くなる人が出れば話は別です。法律上の相続分は丸子さんが2分の1で、息子さんらが4分の1ずつです。このうち丸雄さんと同居しているのは誰ですか。
【丸雄】妻と長男一家です。
【弁護士】丸雄さんご自身は遺言を作ることについてどう思っていらっしゃるのですか。
【丸雄】息子たちは別に仲が悪いわけじゃないし、財産って言っても自宅くらいしかないから遺言なんて大げさなものは必要ないと思うんですけどね。
【弁護士】そうなんですね。相続事件はたくさん扱っていますが、親の生前は兄弟仲が良かったのに親の死後に揉めているという事件は多いです。あとは、兄弟仲がよくても、その配偶者が相続に口を出してくるということがよくあります。例えば、今回ですと、次男さん自身は財産はいらないと思っていたとしてもその妻も同じ考えとは限らないわけです。
【丸雄】息子らの奥さんが全く口を出してこないかというと自信ないなぁ。
【弁護士】また、財産についてですが、預貯金が少なくて、自宅と土地だけがあるというのは一番揉めるパターンです。不動産は預貯金と違って簡単には分けられないからです。安い不動産であれば相続人の一人が不動産を取得して、その代わりに他の相続人に相続分相当のお金を払うことでまだなんとか調整することができます。しかし、不動産の価値が高い場合は、そのような調整も難しいです。特に都内では、自宅の土地の評価が思いのほか高くなっている場合が多いので注意が必要です。
【丸雄】もし自宅を売ってお金にして分けるなんてことになったら、自宅に住んでいる長男一家は困っちゃうだろうし、うちはむしろ遺言を作った方がよいパターンな気がしてきました。どうやって作ればいいですか。
【弁護士】遺言は大きく分けて2種類ございまして、自筆証書遺言というものと、公正証書遺言というものです。自筆証書遺言というのはよくドラマとかで出てくる手書きの遺言のことですね。
【丸雄】私はその手書きのやつをイメージしてきました。もう一つの公正証書遺言というのは何ですか。
【弁護士】公証役場という役所で作ってもらえる遺言です。少し余分に費用がかかりますが、いつ誰がどういう内容で作ったかを記録・保管してもらえるので、後で、いつ誰が作った遺言なのかで揉めることがないのですよ。また、紛失や盗難の心配もありません。
【丸雄】確かに、ドラマだと、遺言を見つけた相続人が自分に不利な遺言をこっそり捨てただとか、手書きの遺言が偽造だとかで争いになっていますもんね。遺言を作ったのに揉めたら意味がないし、せっかくだから公正証書っていうのにしてみようかな。
【弁護士】そうされる方のほうが多いですね。
【丸雄】公正証書遺言の作成を弁護士さんにお願いした場合、費用はどんな感じですか。
【弁護士】公正証書遺言の場合、費用は、公証役場に支払う手数料と、弊所にお支払いいただく弁護士費用になります。順番にご説明していきますね、まず公証役場に払う手数料ですが………
◇◆
いかがでしたでしょうか。法律相談の様子が少しはイメージしていただけましたでしょうか。このように相談される方ご自身の考えや気持ちがまだまとまっていない場合でも、弁護士が質問を繰り返して状況を正しく把握することで、問題点や正しい方針を見つけることができます。ぜひお気軽にご相談ください。